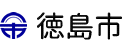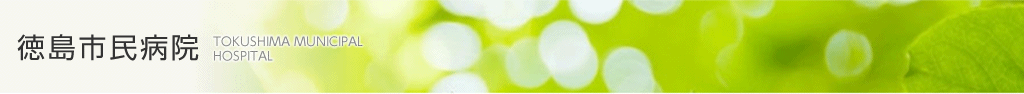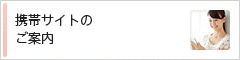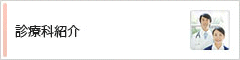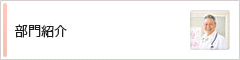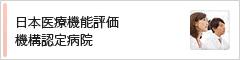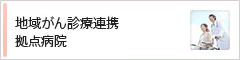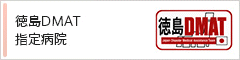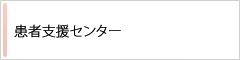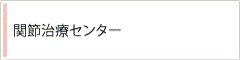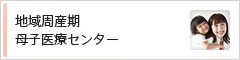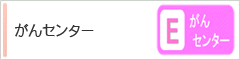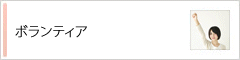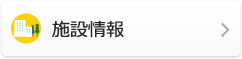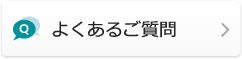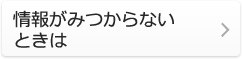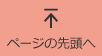肝臓・胆道(胆嚢/胆管)・膵臓外科
最終更新日:2023年4月1日
診療科の紹介
肝臓・胆道(胆嚢、胆管)・ 膵臓・脾臓領域の病気に幅広く対応しています。特に主となるのはがんの治療となりますが、この領域のがんの多くは早期発見が困難なため、診断された時点である程度進行していることが多く、正確な進行評価による治療方針決定が必要となります。がんの根治性を得るためには大きな手術(高侵襲の手術)、難しい手術(高難度の手術)が必要になることも多く、 常に患者さんの安全を第一に考え治療方針を決定しています。
現在、日本肝胆膵外科学会では、肝胆膵領域における専門的知識及び熟練した技能を備える外科医に対し、日本肝胆膵外科学会高度技能専門医(指導医)として認定しています。当科では2名の専門医が在籍しており、移植を除く全ての高難度手術の実施が可能となっています。また、この領域の内視鏡下手術も適応症例を慎重に検討し、積極的に導入しています。
手術は月曜日から金曜日まで行っており、急性胆嚢炎などの緊急疾患に対しては夜間休日を問わず随時対応を行っています。
取り扱っている主な疾患
1. 肝臓
原発性肝がん(肝細胞がん、肝内胆管がんなど)、続発性肝がん(多臓器がんからの転移)、肝内結石症、肝良性腫瘍(肝血管腫など)、肝膿瘍、肝嚢胞など
2. 胆道
胆管がん、胆嚢がん、十二指腸乳頭部がん、胆石症、胆嚢炎、先天性胆道拡張症、膵・胆管合流異常症など
3. 膵臓
膵がん、膵嚢胞性疾患(IPMN、MCNなど)、内分泌腫瘍、慢性膵炎など
4. 脾臓
血液疾患(特発性血小板減少性紫斑病など)、肝硬変症に伴う脾機能亢進症、悪性リンパ腫などの腫瘍性疾患
代表的な疾患の診断、治療方針
1. 肝臓
(1)肝細胞がん
腫瘍個数、大きさ、肝機能に基づいて治療方針を決定します。肝切除術、ラジオ波焼灼術、経肝動脈的化学塞栓術(TACE)、化学療法などの治療を行っています。
(2)肝内胆管がん
肝臓内の胆管から発生した悪性腫瘍であり、手術治療が最も成績がよく、積極的に肝切除や胆管切除を行っています。
(3)転移性肝がん
肝臓以外に発生したがんが肝臓に転移したものであり、発生臓器により治療方針が変わります。大腸がんからの肝転移は、手術により根治が目指せる可能性があり、化学療法も組み合わせて、積極的な手術治療を行っています。
2. 胆道(胆管・胆嚢)
(1)胆石症(胆嚢結石、総胆管結石)、胆嚢炎
胆嚢結石症に対し腹腔鏡下手術を標準術式とし、症例によっては単孔式(小さな1つの創で手術を行う)にて創部のより良い整容性を目指しています。胆嚢炎は発症時期や併存疾患などを考慮し、早期手術や経皮的胆嚢ドレナージ後の待機手術を行っています。
総胆管結石症に対しては、内科による内視鏡下結石除去を基本としていますが、困難例などには手術(開腹or腹腔鏡下手術)を行っています。
(2)胆管がん・胆嚢がん
胆道がん(胆管がん、胆嚢がん)に対しては、病変部位により肝切除術、胆管切除術、膵頭十二指腸切除術を行っています。肝切除範囲が大きくなる場合は、残る肝臓を肥大させるために術前に門脈塞栓術を行ってから肝切除を行っています。
3. 膵臓
(1)膵臓がん
膵臓がんに対しては、病変の部位により膵頭十二指腸切除術や膵体尾部切除術を行っています。消化器がんの中では最も治療が困難な疾患であり、化学療法や放射線治療を組み合わせ治療成績向上に努めています。
(2)他の膵腫瘍
良性や低悪性度腫瘍(IPMNなどの嚢胞性腫瘍や内分泌腫瘍)に対しては、積極的に腹腔鏡下手術や縮小手術(機能温存)を取り入れています。
4. 脾臓
血液疾患(特発性血小板減少性紫斑病など)、肝硬変症に伴う脾機能亢進症、悪性リンパ腫などの腫瘍性疾患に対して、腹腔鏡(補助)下脾臓摘出術を行っています。
医師紹介
| 職名 | 氏名 | 認定資格 | 専門分野 |
|---|---|---|---|
診療部長 兼 |
金村 普史 | 日本外科学会専門医・指導医 |
消化器外科 |
| 主任医長 | 近藤 愛貴美 | 日本外科学会専門医 |
一般外科 |
| 名誉院長 | 三宅 秀則 | 外科学会専門医 消化器外科学会専門医 消化器病学会専門医 肝臓学会専門医 日本肝胆膵外科学会高度技能指導医 日本癌治療認定医 |
消化器外科 |
学会施設認定
日本肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設(B)
日本肝臓学会認定施設