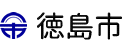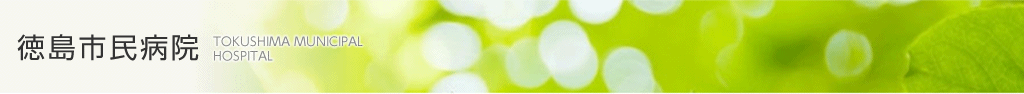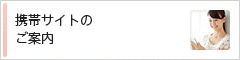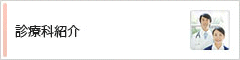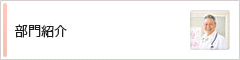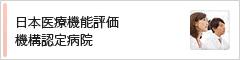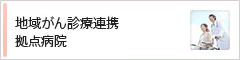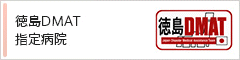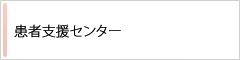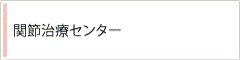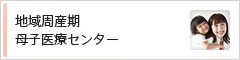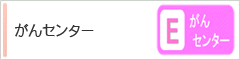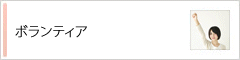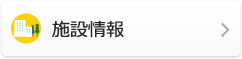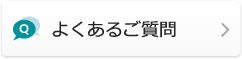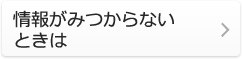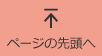麻酔科
最終更新日:2024年3月1日
診療科の紹介
患者さんが安心して手術を受けられるよう、質の高い周術期の麻酔・全身管理を心がけています。

総括部長 野崎 淳平
麻酔科は、1979年(昭和54年)に開設されました。その後常勤医のいない時期もありましたが、現在は常勤の麻酔科医5人および徳島大学麻酔科の非常勤医師1名が麻酔業務に専従しています。
市民病院では、年間3,800例以上の手術症例があり、そのうち局所麻酔を除く2,450例あまりが麻酔科管理となっています(2021年度実績)。
取り扱っている主な疾患
当院で行われる手術検査症例において各科より麻酔科管理を依頼された症例
代表的な疾患の診断、治療方針
現在、徳島市民病院では、年間2,500例を越える麻酔科依頼の麻酔管理症例があります。
この一例一例に対して術前回診を行い、事前に麻酔計画を立て、十分な検討の後、全身麻酔や区域麻酔を実施しています。
術中は注意深い観察を行うとともに、異常発生時には迅速かつ適切な処置を施すことで、患者さんの安全を確保しています。
また、術後の疼痛管理を考慮した管理を術中から行っています。
麻酔方法
全身麻酔と区域麻酔をそれぞれ単独で行う場合と、両者を併用する場合があります。
また、手術中の全身状態に応じて麻酔法を変更することもあります。
これらは、患者さんごとに、担当の麻酔科医が最も安全と考えられる麻酔法を選択します。
全身麻酔
一般的な全身麻酔は静脈麻酔薬、筋弛緩薬により入眠後、気管挿管等により気道を確保し、吸入麻酔薬や静脈麻酔薬、鎮痛薬等を使用して手術中の麻酔を維持します。
区域麻酔
- 硬膜外麻酔
硬膜外麻酔は、脊椎(背骨)の中にある脊髄のすぐ近くの硬膜外腔という場所に、 麻酔薬をいれて、手術部位の痛みを無くす、あるいは軽くする麻酔法です。
手術をする所に合わせて、背中のどこから麻酔薬をいれるかを決め、カテーテルという細い管をいれます。 このカテーテルから麻酔薬をいれて麻酔を行います。
- 脊髄くも膜下麻酔
脊髄くも膜下麻酔は、細い針を使って脊髄液が満たされている場所に局所麻酔薬をいれ、脊髄を一時的に麻痺させます。
この麻酔が効いている間(3~6時間)は、感覚が無くなり、足を動かせなくなります。
- 末梢神経ブロック
神経の走行に沿って麻酔薬を注射し、その領域の痛みをとる方法です。 麻酔の範囲は、硬膜外麻酔や脊髄くも膜下麻酔より狭く、必要最小限にとどめられることが特徴です。
末梢神経ブロックのみでも短時間の手術を行うことができますが、通常は、全身麻酔と併用して手術後の痛み止めに利用します。
上肢の神経ブロックでは首の横側や脇の下、鎖骨の近くから針を刺します。 下肢の神経ブロックでは足の付け根やおしりから針を刺します。超音波装置(エコー)や電気刺激、患者さんの感覚などで確認してから麻酔薬をいれます。また腹部の神経ブロックでは全身麻酔後に、超音波装置を使用して主に筋層に麻酔薬をいれます。
術後疼痛管理
最近では、痛みが強くなった時に、患者さん自身で使用できる鎮痛法があります。
硬膜外麻酔のカテーテル、または、点滴から痛みを和らげる薬が持続的に入っていて、それでも痛いと感じた時は、 さらに自分自身でボタンを押すことで、痛みを軽くすることができます。 この方法を患者管理鎮痛法(PCA)といいます。
当院でもこれらを使用して術後の疼痛緩和を積極的に行っています。
医師紹介
職名 |
氏名 | 認定資格 |
専門分野 |
|---|---|---|---|
総括部長 兼 臨床工学室長 |
日本麻酔科学会指導医・認定医 |
麻酔科 |
|
主任医長 |
日本麻酔科学会専門医・指導医 |
麻酔科 |
|
| 主任医長 | 合田 かおる | 日本麻酔科学会認定医 | 麻酔科 |
| 専攻医 | 塩崎 友里子 | 麻酔科 | |
| 専攻医 | 前田 卓哉 | 麻酔科 | |
| 専攻医 | 岡本 将裕 | 麻酔科 |
診療実績(2021年)
予定手術 2,191例、緊急手術 264例
| 脳神経・脳血管 | 36 | |
| 胸腔・縦隔 | 77 | |
| 上腹部内臓 | 199 | |
| 下腹部内臓 | 696 | |
| 帝王切開 | 26 | |
| 頭頸部・咽喉部 | 243 | |
| 胸壁・腹壁・会陰 | 195 | |
| 脊椎 | 3 | |
| 股関節・四肢 | 974 | |
| その他 | 6 |
| 全身麻酔(吸入) | 1,105 | |
| 全身麻酔(TIVA) | 101 | |
| 全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝達 | 908 | |
| 全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝達 | 297 | |
| 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 | 21 | |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 7 | |
| その他 | 16 |
性別
男性 909例、女性 1,546例
学会施設認定
日本麻酔科学会麻酔科認定病院 (認定第416号)