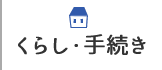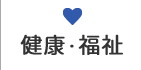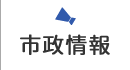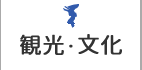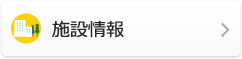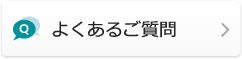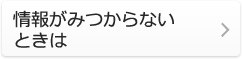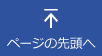6月定例会で可決した決議・意見書
最終更新日:2025年7月31日
「徳島県平和の日」の条例制定を求める意見書
昭和20年7月4日、徳島市は、大空襲により住宅区域の74%が焼失、市内人口の約6割に上る7万人以上が被災し、死者1,000人、負傷者2,000人を超えるという未曽有の悲劇を経験した。徳島県内では、この徳島大空襲以外にも少なくとも35か所で空襲を受けており、死傷者は600人以上にも及んでいる。
この歴史的事実は、戦争の惨禍と平和の価値を市民・県民に深く刻むものであり、戦争を知らない世代が増える中、今後誰一人として再び戦禍に巻き込まれないよう、決して風化させることなく、次の世代へと語り継いでいかなければならない。
徳島県は、県を挙げて核兵器の廃絶と世界の恒久平和実現を目指す意思を内外に表明するため、昭和57年に全国に先駆けて「非核の県」宣言を行っている。世界情勢が再び緊迫する中、平和国家日本の一員として世界の都市と連携し、文化交流の推進に努め、人々の相互理解に立脚した国際秩序の形成と平和の実現を目指すことは、「非核の県」宣言の趣旨に沿ったものであると言える。
このような背景を踏まえ、徳島大空襲から80年目となる節目の年に、徳島大空襲のあった7月4日を「徳島県平和の日」と定める「徳島県平和の日」条例を県として制定することは、市民・県民の平和意識を一層高め、持続可能な平和社会の構築に寄与するものである。
よって、徳島県においては、「徳島県平和の日」条例を制定し、市民・県民の平和意識の高揚と基本的人権の尊重を図られるよう、強く求める。
生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議
生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会の調査経費について、200万円追加し、300万円以内とする。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。