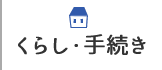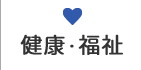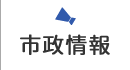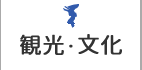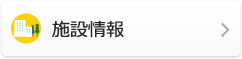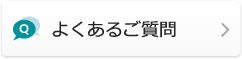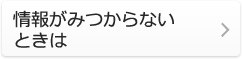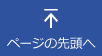家庭でできる浄化対策
最終更新日:2025年12月12日
川や海に流れ込む水には、雨水や工場、農業、畜産などからの排水のほか、私たちの暮らしからの生活排水があります。生活排水に含まれる汚れはBOD(生物学的酸素要求量)の量で1人1日約40グラムといわれており、貴重な水を汚す大きな原因のひとつとなっています。
下水道や合併処理浄化槽などの生活排水処理施設が整備されていない場合、生活排水が直接放流されて、近くの水環境に悪影響を与えることになります。
○生活排水とは
生活排水とは、私たちの日常の生活から出される排水のことで、台所・風呂・洗濯などの生活雑排水とトイレからの排水を合わせたものです。
キッチンからの排水が一番汚れています
生活排水に含まれる汚れのうち、台所の割合が最も多く、45%を占めています。これは台所からの排水に、調味料や油脂類などの有機物が多く含まれているからです。余った味噌汁や残った煮汁などを流さない工夫が必要です。
・台所には、目の細かいストレーナーや三角コーナーを設置したり、水切り袋を使用するなど、調理くずや食べ残しを流さないようにしましょう。
・飲み物は、飲めるだけグラスにそそぎましょう。食事は食べきれる分だけつくりましょう。
・お米のとぎ汁は、洗浄効果があり、食器のつけおき洗い等に利用できます。また、養分を含むので、植木の水やりに使うと、よい肥料になります。
・使用した食用油は、流さないでください。そのまま流すと河川を汚す大きな原因となるだけでなく、排水管をつまらせ、悪臭の原因にもなります。残った食用油は、料理の工夫で使い切るようにしましょう。捨てる際は、新聞紙や古布にしみこませ燃えるゴミとして出すか、ペットボトルに入れて市のエコステーションに持ち込みましょう。
・食器を洗う前に、油汚れなどはふき取りましょう。古布やゴムべらなどで拭き取ってから洗い流したり、アクリルたわしなどを使用して、洗剤の使用量を減らしましょう。
風呂、洗濯の際には、次のことに気をつけましょう
・石けん、洗剤は適量に使いましょう。目分量は使いすぎのもとです。計量スプーンなどで正しく計り、使用するようにしましょう。
・シャンプー・リンスは適量を使いましょう。
・風呂の残り湯は、洗濯、掃除、打ち水などに使いましょう。残り湯は、冬場でもその翌朝は温かく、水道水より高い洗浄力が得られます。
・排水溝の髪の毛などはこまめに取り除くようにしましょう。
正しく使おう「浄化槽」
浄化槽は、下水道が整備されていない地域の住宅などに設置されている、微生物の働きを利用して、暮らしの中の汚れた水をきれいにする装置です。間違った使い方や維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生することがあります。
○保守点検
浄化槽の稼働状況の確認、機器の調整、消毒薬の補充などを行います。県知事の登録を受けた業者に委託して行います。
○清掃
浄化槽内で発生した汚泥などの引き抜きや洗浄などを行います。市長の許可を受けた業者に委託して行います。
○法定検査
保守点検や清掃が適正に実施されているか確認する検査です。県内では公益社団法人徳島県環境技術センターが指定検査機関となっています。
生活排水対策パンフレット(川や海をみんなできれいに)
徳島市では、生活排水対策の普及啓発を推進するために、パンフレットを作成・配布しています。地域の活動などで配布を希望する場合は、担当までお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。